コラムCOLIMN
- コラム
- BGMでの快適なオフィス環境作り
- 労働生産性とは?定義と計算式について
BGMでの快適なオフィス環境作り
労働生産性とは?定義と計算式について

近年、働き方改革が進むなか、企業の労働生産性に多くの関心が持たれています。しかし、生産性の向上を求められても、具体的な向上策が分からない経営者も多いことでしょう。日本の労働生産性は、国際的に見ると「36ヶ国中20位」に位置しています。これは、日本全体において効率の良い働き方ができていないということです。
今回は、企業における労働生産性について詳しく解説するとともに、労働生産性を向上させるメリットやポイントを説明します。さらに、国際社会における労働生産性との違いについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
労働生産性とはなにか?
働き方改革の一環として、さまざまな企業が「ノー残業デー」や「テレワーク」「有給休暇取得」などを推進しています。そのような改革で目指すべきゴール地点は、国際社会における労働生産性を向上させて国力を高めることです。国際社会における労働生産性については後述しますが、まずは企業における「労働生産性」について説明していきます。
「生産性」の定義について
公益財団法人日本生産性本部では、以下のように定義づけています。
”生産性とは、生産諸要素の有効利用の度合いである”
(引用:https://www.jpc-net.jp/movement/productivity.html)
計算式は「生産性=産出÷投入資源」となります。「投入資源」と「産出」の意味は、次のとおりです。
・投入資源:モノを作り出すときに必要な「材料・人件費・土地・設備」などのコスト
・産出:投入資源を使って作り出されたモノや成果
つまり生産性とは、投じた資源に対して生み出された成果の割合を示したものです。例えば、投じた資源の割合を上回る売上を出した場合は、「生産性が高い」といえます。反対に、モノを生み出すためにかけたコストの割に売上が低かった場合には、「生産性が低い」といえるわけです。
「資本生産性」と「労働生産性」に分かれる
生産性は、次のように「資本生産性」と「労働生産性」に分けることができます。
・資本生産性:投入した資本でどのくらいの成果を上げられたのかを数字で示したもの
・労働生産性:投入した労働でどのくらいの成果を上げられたのかを数字で示したもの
つまり、資本生産性はモノに対して使われる言葉で、労働生産性は人(働く人々)に対して使われる言葉です。
資本生産性は資本の成果を数値化したもの
ここで投入される資本とは「材料・土地・設備」などを指します。工場を例に挙げて説明しましょう。工場における動作効率の向上を図るべく、最新のシステムを投入したとします。そこで、従業員がしっかりとシステムを使いこなせれば工場の動作効率が高まるでしょう。しかし、従業員がうまくシステムを使えない場合、システムにお金をかけたのに動作効率は向上しません。つまり、その状態は「資本生産性が落ちている」と言い換えることができます。
労働生産性は労働者の成果を数値化したもの
一方、労働生産性では「働き手1人当たり、または1時間あたり」で生み出せる成果を数字で表します。具体的には、働き手一人ひとりのスキルや能力がアップすれば、同じ時間働いていてもより多くの成果を生み出すことができるというものです。そのため、労働生産性を効率よく高めるには、働き手のスキル向上が重要だといえるでしょう。なお、労働生産性をさらに細かく分類すると「物的労働生産性」と「付加価値労働生産性」に分けることができます。こちらについては後述します。
労働生産性の計算式
労働生産性を把握するにあたり、知っておくべき基本的な計算式は、次のとおりです。
【労働生産性=産出(生み出された成果や付加価値額)÷労働量(労働者数や労働者数×労働時間)】
会社の生産性を把握したい方は、数値を当てはめて計算してみてくださいね。
労働生産性を高めるには?
企業のパフォーマンスを高めるには、先述のとおり、従業員一人ひとりのスキルや能力をアップさせることが重要です。働き手一人ひとりのスキルがアップすれば、生み出せる成果も大きくなります。同じ人数で成果が大きくなれば、効率性が良くなったといえますよね。また、単純に計算式の分母となっている「労働量」を減らすことも有効な方法です。働き手の人数を減らしたり、人数は変えずに勤務する時間を減らしたりすることで分母の数値を減らして生産性を上昇させます。ただし、人数を減らしたり勤務する時間を減らしたりすることで、成果も同時に減ってしまっては意味がありません。この記事の後半では、生産性を上昇させるポイントを説明しますので、ぜひ参考にしてください。
労働生産性はさらに2種類に分類できる
労働生産性は「物的労働生産性」と「付加価値労働生産性」に分けられることを先に述べました。ここでは、この2つについて解説します。
物的労働生産性とは?
物的労働生産性とは、成果を目に見えて数えられる「生産量」や「販売金額」などで算出した値のことです。非常にわかりやすく簡単に計算できることから、社外への資料などでもよく用いられます。これによって、従業員1人がどのくらいの生産量や販売金額などをあげているのかを明確に把握することが可能です。
物的労働生産性の計算式と例
計算式は、以下のとおりです。
【従業員1人あたりの物的労働生産性=生産量(成果)÷労働力(労働者数)】
【1時間あたりの物的労働生産性=生産量(成果)÷労働力(労働者数×労働時間)】
例えば、とある工場にて1万個のグラスが生産されたとします。その際、働いていた従業員が500人だとすると「1万個÷500人=20個」という計算です。要するに、この工場では従業員1人あたり20個のグラスを生産することができるわけです。言い換えると、労働者1人あたりの生産性は「グラス20個分」ということです。
また、1時間あたりの生産性を算出する場合は、労働時間を事前に確認しておく必要があります。具体的には、1万個のグラスを500人の従業員が10時間かけて生産したと仮定しましょう。これを計算式に当てはめると「1万個÷(500人×10時間)=2個」となります。つまり、この工場の1時間あたりの生産性は、「グラス2個分」といえるわけです。
付加価値労働生産性とは?
次に、付加価値労働生産性について説明します。こちらは、成果の部分を「付加価値」として算出した値のことです。この場合の付加価値とは、会社が商品やサービスを生産したことで新しく生まれた金銭的な価値を指します。
付加価値労働生産性の計算式と例
計算式は、以下のとおりです。
【従業員1人あたりの付加価値労働生産性=付加価値の値÷労働力(労働者数)】
【1時間あたりの付加価値労働生産性=付加価値の値÷労働力(労働者数×労働時間)】
具体例を挙げて説明します。グラスを1つ生産するときに原価100円がかかったと想像してください。そのグラスを300円で販売すると、販売金額から原価を引いた差額である200円がグラス1個の付加価値となります。そして、1個のグラスで200円の付加価値ですので、1万個のグラスの付加価値は200万円です。
先ほどと同じ条件で計算してみましょう。もしも、従業員1人あたりの付加価値労働生産性を算出したい場合には「200万円÷500人=4,000円」と計算できます。また、1時間あたりの生産性を算出する場合は「200万円÷(500人×10時間)=400円」です。
「付加価値」は粗利益と似ている
さらに詳しく説明すると付加価値とは、経常利益・減価償却費・人件費の3つが組み合わさった値です。この考え方は、粗利益とよく似ています。粗利益とは、売上高から売上原価を引いた差額の収益のことです。もしも、付加価値をイメージしにくいという人は、粗利益と似ていると覚えておくと良いでしょう。
人件費の計算で注意すべき点
付加価値に含まれている「人件費」を求めるときに注意していただきたい点があります。人件費とは、単純に「従業員の給与」だけではありません。給与のほかにも、社会保険料や交通費、会議費用など従業員にかかったすべての費用が含まれます。そのため、漏れのないように注意して人件費を計算してくださいね。

オフィスにBGMという発想を。オフィスにBGMを流すだけでポジティブな効果がたくさん!
オフィスには「オフィス専用」のBGM、ぜひ試してみませんか?
労働生産性が高い企業と低い企業の違い
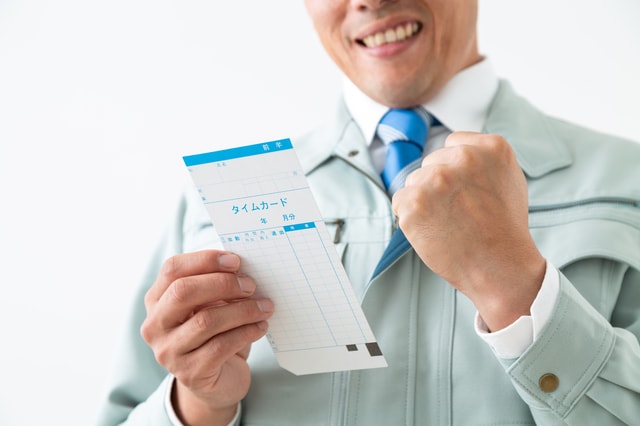
次に、労働生産性が高い企業と低い企業の特徴を説明します。
労働生産性が高い企業の特徴
労働生産性が高い企業とは、投入した労働力を上回る成果を生み出せている効率の良い企業をいいます。そのような効率が良い企業には、以下2つのような特徴があります。
高い社会的感受性を持った人が組織にいる
ビジネスにおいて効率の良さを発揮できる企業のなかには、高い社会的感受性を持った人が多くいます。「社会的感受性」とは、職場のなかで周囲の人の感情や要望を理解できる性質のことです。社会的感受性が高い人は、周囲の人が思っていることや望むことを汲み取ったうえで行動することができます。言い換えれば、リーダーシップがある人のことだといえるでしょう。
職場や組織の中に、社会的感受性の高い人がいればビジネスがスムーズに進むため、効率よく成果を生み出すことができます。
主体的な行動ができる人が多い
労働生産性の高い企業のもう1つの特徴は、主体的な行動ができる人が多いことです。「主体的」とは、よく分からない状況にあっても、自分が何をすべきかを理解して行動することをいいます。似たような言葉に「自主的」がありますが、こちらは、状況がよく分かっている場合に、何をすべきかを理解して行動することです。
ビジネスの場面では、「自分が今何をすべきなのか」を常に指示してもらえるとは限りません。自分の経験や能力で、「今何をすべきなのか」を瞬時に理解して行動できる人が多い企業は、労働生産性を高めることができるのです。
労働生産性が低い企業の特徴
続いて、労働生産性が低い企業の特徴を見ていきましょう。労働生産性が低い企業とは、投入した労働力を下回る成果しか生み出せず、効率の悪いビジネスをおこなっている企業です。
粗利益を生み出せずに労働時間が長い
生産性が低い企業の多くは、粗利益を生み出せず、長時間労働になっていることがあります。単価の低い仕事ばかりを請負い、粗利益を生み出せないために人件費を捻出できません。
さらに粗利益を生み出すことに集中しすぎて、多量の労働力を投入します。企業によってさまざまですが、従業員数を増やしたり、人数は変えずに労働時間を増やしたりという方法をとるのです。しかし、これでは人件費を膨大に増やしてしまうだけで、負のループに陥いることになります。
労働生産性の低い企業は、生産性の低さ自体を労働力でカバーしなければ、企業が立ち行かない状況になっているのです。この場合、まずは長時間労働を改善する必要があります。
業種別の労働生産性について
今度は、業種別の視点から労働生産性について見ていきましょう。
労働生産性が高いのは製造業や金融業
一般的に、労働生産性が高いといわれる業種は「製造業」や「金融業」です。これらの業種は、投入した設備や機械などが効率よく稼働すればするだけ、生産性を高めることができます。従業員一人ひとりのスキルや能力に大きく左右されることなく、事業を運営していけることが特徴です。
特に製造業では、働く従業員が時代とともに減少する傾向にあります。これは、IT技術の発達に伴ってAIロボットなどを導入し、人件費を削減しているからです。先述したとおり、労働生産性を高めるためには、投入する労働力を減らすことが有効な手段といえます。こうしたことから、製造業や金融業は生産性の高い業界なのです。
労働生産性が低いのはサービス業や医療
対して、労働生産性が低いといわれている業界は、「サービス業」や「医療」です。この場合のサービス業とは、飲食や宿泊、娯楽などの総合的なものとなります。特に、飲食や宿泊のサービス業では、サービスによって得られる付加価値は非常に大きいものの、そこには大量の労働力を割かなければなりません。
例えば、1人のお客様を満足させるためのサービスをするときに、複数人の従業員で対応させる必要があります。医療についても同じことがいえます。医療業界にはハイスペックな機械が揃っているので、設備投資で生産性を向上させているイメージを持っている人も多いかもしれません。しかし、1人の患者を治療するためには複数人のスタッフが必要です。
このように、生み出される成果に比して投入する労働力が大きいことから、サービス業や医療は生産性が低い業界として知られています。
サービス業の生産性を高めるのが日本の課題
日本にはさまざまな仕事があるなか、サービス業で働く人は多いでしょう。サービス業では多くの労働力を投入しなければならないため、必然的に雇用する従業員の人数も増えるからです。
しかし、この事態を生み出している1つの原因として「日本の過剰サービス」が考えられます。日本のサービスは、世界にも誇れる素晴らしいものです。しかし、より良いサービスを追求すればするほど、そこに割く人件費は大きく膨らんでいきます。サービス業の人手不足が加速し、労働生産性が高いとされている製造業などからサービス業に労働者が流れてしまえば、国全体の生産性も落ちてしまうことでしょう。
労働生産性を向上させるメリット
ここで、労働生産性を向上させるメリットを3つ紹介します。メリットを知ったうえで、企業としての生産性を高めることを検討してみてください。
企業の利益向上や従業員の給料上昇
企業の労働生産性が向上すれば、利益の向上や従業員の給料上昇につなげることができます。投入した労働力に対して得られる成果が大きければ、それだけ企業としての利益も上がりますよね。そして、企業の利益が上がれば、従業員の給料も上げることが可能になるわけです。
従業員の給料が上昇すれば、従業員のモチベーションを保つことができます。昇給した従業員は、ますます仕事に対してやる気を発揮してくれるかもしれません。このように、労働生産性を向上させることは、企業をプラスの方向に導いてくれるメリットを持っています。
顧客満足度の向上
企業の労働生産性が向上すれば、企業全体のレベルアップを図ることが可能です。例えば、グラスを生産している工場で労働生産性が高まると、利益を元に設備投資ができて、より良いグラスを生産することができます。
そうなれば、さらに生産量を増やして安定的な供給を維持していけるようにもなるでしょう。その結果、顧客に滞りなく商品を提供することができるため、顧客満足度の向上につなげることができます。
国から補助金や優遇措置を受けられる
「生産性の向上に努めている」と国から認定された企業は、さまざまな優遇措置を受けることができます。具体的には次のとおりです。
・設備投資の際にかかる固定資産税が、3年間だけ2分の1になる
・日本政策金融公庫による低利融資(金利が0.9%引き下げられる)…など
また、労働生産性を高める際に、厚生労働省が定めている「生産性向上の条件」を満たすことで、補助金や優遇措置を受けることもできます。例えば、以下のような助成金が割増対象です。
・労働移動支援助成金
・中途採用等支援助成金
・地域雇用開発助成金
・人材確保等支援助成金
・両立支援等助成金
・キャリアアップ助成金
・業務改善助成金…など
(※2020年現在)
このほかにも、生産性を向上させるために「ITツール」を導入する企業向けに、一部の費用を負担してくれる「IT導入補助金」などもあります。もしも、設備投資をしたいけれど費用のことで悩んでいる方は、こういった制度も活用することをおすすめします。
地方自治体からの補助金制度もある
上記で紹介したのは国からの補助制度ですが、地方自治体が生産性向上のために設けている補助金制度もあります。補助金対象者として、市内に活動拠点を置いている中小企業や市税の滞納をしていない人など、さまざまな条件がありますが活用してみてください。
労働生産性を向上させるポイントは?
続いて、労働生産性を向上させるポイントについて解説していきます。
長時間労働を減らす
ポイントの1つ目は、長時間労働を減らすことです。労働生産性が低い企業の特徴でも述べたとおり、労働生産性を低下させている原因の1つに「長時間労働」があります。
従業員は、労働時間が長くなるほど集中力が途絶えてモチベーションを保つことができません。粗利益を得られないために人件費を捻出できず、結果的に従業員一人ひとりの作業量が増えて長時間労働になってしまいます。
まずは、長時間労働を減らすことをおすすめします。粗利益が得られない以上、労働時間を長くするしか存続できないと考えてしまうのは当然のことです。しかし、労働生産性を向上させるためには、徐々に変化させていくことが大切です。現在雇用している従業員を大切にして、モチベーションを保つことが生産性の向上につながるでしょう。
経営効率の改善を目指す
ポイントの2つ目は、経営効率の改善を目指すことです。経営効率の改善とは、具体的に以下のようなことです。
・投入資源を減らす:事業の見直しや不必要なコスト削減をすることで、生産量は変わらずとも生産性の向上につながる
・成果を増やす:労働者の能力向上や値上げなどにより、投入する労働力は変わらずとも生産性の向上を図ることができる
・規模の簡素化:収入よりも支出が多い「不採算部門」や人件費を削減することにより、投入と産出の両者を削り、全体的に生産性を向上させる
・規模の拡大化:部門の増設や新事業立ち上げなどにより、投入を増やすことで産出も増やしていく
このように、経営戦略を見直すことで経営効率の改善を目指します。どれも有効的な方法なので、企業の性質に合わせて選んでみてください。
労働者のスキルアップや業務効率化
最後のポイントは、働く従業員一人ひとりのスキルアップや業務効率化を図ることによって労働生産性向上を目指すことです。従業員のスキルアップをさせるためには、社内研修や自己研鑽できる制度を取り入れる必要があります。さらに、スキルアップした従業員に対して手当をつけるなどの対応も求められるかもしれません。
また、ITツールなどの設備投資によって業務効率化を図ることも大切です。例えば、人間がわざわざおこなう必要がない仕事などを機械化することで、その分の労力をほかの仕事に回すことができます。
このようにして、従業員一人ひとりのスキルアップや業務効率化を図ることができれば、1人が生み出せる成果もより大きいものとなって生産性向上につなげることが可能です。
国際社会で見た日本の労働生産性
ここまでは企業単位の話でしたが、ここからは国単位について解説します。企業における生産性と国際社会における生産性は、厳密にいうと異なるのです。
国際社会の労働生産性とは?
国際社会における労働生産性を計算する際には、一般的に「付加価値」を基本とした方法で計算されます。そして、ここで用いられる付加価値とは「GDP(国内総生産)」のことです。別名、「国民経済生産性」とも呼ばれています。労働生産性を語るときには、企業と国際社会のどちらなのかを明確にしておかなければ混乱してしまうので注意しておきましょう。
国際社会の労働生産性の計算式
計算式は、次のとおりです。
【(1人あたり)国際社会の労働生産性=GDP÷国内の年間平均就業者数】
【(1時間あたり)国際社会の労働生産性=GDP÷(国内の年間平均就業者数×労働時間)】
計算式そのものは企業の生産性を求める式と似ていますが、付加価値であるGDPを用いている時点で別物だといえます。
労働生産性の国際比較では日本は20位
「公益財団法人 日本生産性本部」が発表している労働生産性の国際比較では、日本は36ヶ国中「20位」と低い順位になっています。上位には主要先進7ヶ国と言われている、アメリカ・ドイツ・イギリス・フランス・イタリア・カナダが名を連ねているなか、日本は最下位となっています。
アメリカと比較してみると、日本の生産性より1.5倍もの数値が計上されています。生産性が一番高いとされているアイルランドとは、約2倍もの差があります。
国民経済生産性と日本の労働時間の関係性
「企業の生産性」と「国民経済生産性」を向上させる方法は同じように考えることができます。
日本の平均年間総実労働時間は、以下のとおり減少傾向にあります。
・1970年:2,200時間以上
・1995年:1,800時間以上
・2015年:1,710時間
(参考:https://honkawa2.sakura.ne.jp/3100.html)
しかし、先ほどのGDPを用いた国際社会における生産性の順位は、ここ数年大きな変化がありません。なぜ、働いている時間が減っているにもかかわらず生産性が向上しないのでしょうか。
それは、このデータが「パートタイマー」を含む全就労者の働いた時間を示しているからです。日本では2000年あたりから、徐々にパートの割合が増えてきました。2018年から2019年までの1年間では、45万人ものパートが増えているのが実情です。(参考:総務省統計局)
パートを除いた正社員の平均労働時間を見てみましょう。
・2016年:2,008時間
・2017年:1,999時間
・2018年:1,998時間
(参考:https://www.keidanren.or.jp/policy/2019/076.pdf)
正社員に焦点を当てて働いている時間を見てみると、1970年あたりの労働時間と大差ありません。画一的に論じるならば、総労働時間や生産性の国際比較を考えると、1970年以降の日本の生産性はあまり変化がないということです。とすると、企業の生産性を高めることは、国民経済生産性を高めることとイコールだといえるでしょう。
労働生産性を向上させて経済活性化を目指そう
この記事では、企業の労働生産性について深く解説するとともに、生産性向上によるメリットや向上させるためのポイントなどについて説明しました。企業の生産性を向上させるには、従業員一人ひとりのスキルや能力のアップ、さらには経営効率の改善も必要です。
また、企業の生産性と国民経済生産性は異なることも紹介しました。異なる2つの生産性ですが、企業の生産性が向上することで、必然的に国民経済生産性も向上します。ぜひ、身近な部分から生産性の向上を図って経済活性化を目指しましょう。

オフィスにBGMという発想を。オフィスにBGMを流すだけでポジティブな効果がたくさん!
オフィスには「オフィス専用」のBGM、ぜひ試してみませんか?




